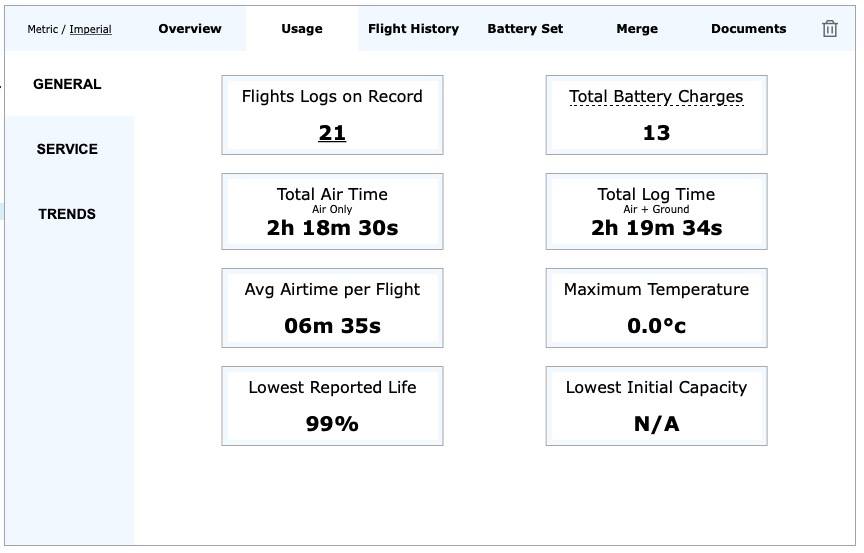SONY Airpeak 体験会に参加させて頂きました。
Airpeak S1は、モーター対角(約644.6mm)のクアッド機体。
機体重量は約3.1kg(バッテリーパック除く)で、最大積載可能質量が約2.5kg。
フライトするには2個のバッテリーが必要で、1個の重量は646g、2個で1.292kgとなる。
最大離陸質量は、7kg。
別売の専用ジンバルGBL-T3はGremsy製で、ダンパープレート、ケーブル装着時で約1.4kgということなので、搭載できるカメラの重量は1.2kgまでという事になるけれど、スペックには「カメラシステム(レンズフィルター、フードなどを含む)の合計重量がおよそ1.1kg以下の組み合わせでお使いください」とある。
詳しくはAirpeak 公式Webを参照していただくとして、かなり明るめな単焦点など、結構多彩なレンズが利用できる。
機体の飛び味はとても良くて、スティックニュートラルでブレーキがかかった状態でもハード的な危うさを感じないサウンドを発する。
実際、プロペラやモーターの作りがとても良いので、とても信頼度は高い印象。
α7sIII +FE 24mm F1.4 GMの場合、合計の質量が1.144kgになるけれど、それらを積んで飛ばした場合でも、かなり手荒に扱っても大丈夫な感じでかっ飛んでいました。
α7sIII 24mmを搭載してのフライト時間は約12分とのこと。。。
Inspire2で18分ぐらいは飛ぶので、そのつもりでいると本番直前にスマートRTHが動作しそう。
バッテリーは上手くやりくりしないと現場撮影で苦労しそうな予感がします。
映像伝送に関してはまだまだ未知で、君津DDFFでのテストでも頻繁にビットレートが落ち、映像フリーズが起きていました。
開発の方に聞いたところ、全て独自に開発したとのことで、まだまだフィールドテストと進化が必要かもしれません。
これは現場に連れ出さないとわかりえないので人柱必至だと思います。
重心のセンターにジンバルが設置されているので、レンズの見切れが激しい。24mmの場合でも前方でもそこそこ映り込む。
14mmなら前進するだけで映り込んでしまうかもしれないが、そもそもよく確認はしなかったけれど、プロペラは早期に写り込んでいるのかもしれません。
さらに、プロペラガードをつけた場合はさらにキツそう。
プロペラガードはサードパーティーに期待とのことで、純正では出さないつもりとのこと。
Gimbalのチルトを割り当てる右肩のダイヤルが、ハード的に遊びがあり、超絶ダメダメなので指摘させてもらい、モニター環境でのシネスコ表示などは未対応なので強く要望。
Appは良く出来ていて練れていけばいい感じになりそう。
送信機2台による2オペは、送信機同士で通信することなく、個別に機体とやり取りするらしく、Inspire2の2オペリンクの苦労はしなくて済む模様。これは大きい。
しかし、マニュアルフォーカスが非対応。。。
50mm F1.2とか開放で使いたいのにフォーカスが送れないのが痛い。
 折ペラでは無く一体型のストレートなプロペラ。モーターへの装着は独自のクイックリリースシステムで精度が高い感じがします。
折ペラでは無く一体型のストレートなプロペラ。モーターへの装着は独自のクイックリリースシステムで精度が高い感じがします。